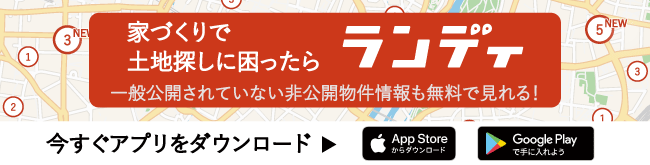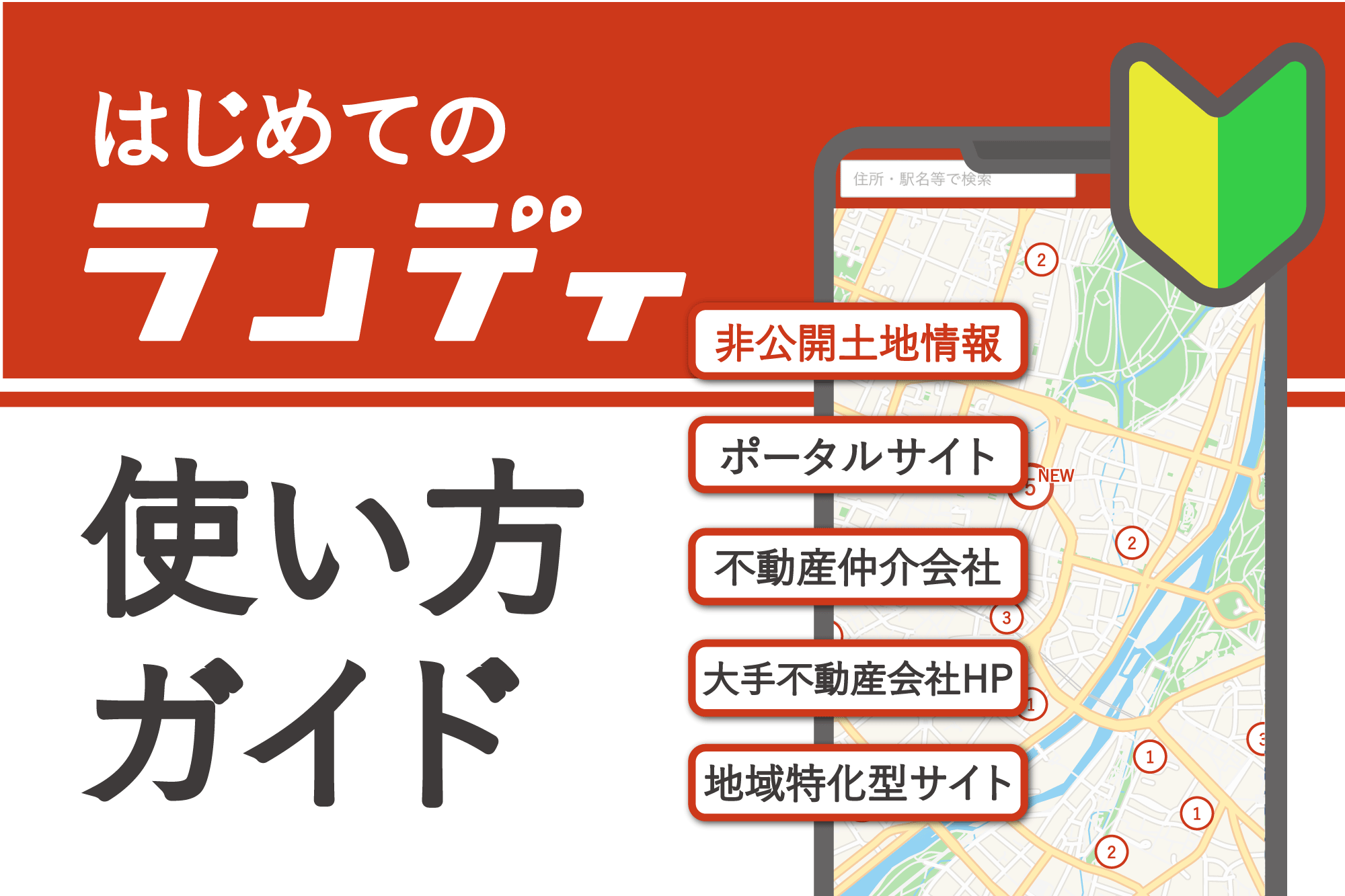お金についてMONEY
自宅の売却の際に発生する税金を分かりやすく解説
記事監修者
 税理士法人VERTEX
税理士法人VERTEX
代表税理士 渡辺秀俊
【保有資格】税理士、行政書士、宅地建物取引士
【専門分野】資産税(相続、事業承継、資産管理)
事業主・地主・不動産オーナーの事業承継対策・相続対策・提案を中心に資産税の専門税理士として従事。
過去の経験により、「節税よりも家族仲良く」をモットーにお金のかからない基本的な対策から物納による納税対策まで幅広い提案と元専門学校講師の経験を生かしたセミナーや個別相談の活動を精力的に行っている。
著書に「不動産オーナー・税理士のための〔不動産×会社活用〕相続対策の方程式(共著 清文社)」「これならできる物納による相続税の納税対策(清文社 共著)」など。
URL https://www.vtx.jp/
自宅の売却で多くの方が悩むのが税金の問題です。複数の要素を考慮したうえで計算をしないと正確な金額は出せません。
本記事では、自宅の売却の際に発生する税金の計算方法や利用できる特例制度を解説します。税金の知識を身に着けると売却後の資金計画が立てやすくなるので、ぜひ参考にしてみてください。
- 自宅の売却には税金がかかる!?
- 譲渡税の計算方法
- 譲渡税がゼロに!?自宅を売却した際の特例制度を解説!
- 確定申告は必要?譲渡税ゼロでも確定申告が必要な場合も
- 税金を正しく理解して、次のマイホーム購入計画を
自宅の売却には税金がかかる!?
自宅の売却には様々な税金がかかります。■ 売買契約書に添付する収入印紙にかかる「印紙税」
印紙税とは、商取引などで使用する文書に対して課税される税金です。住宅購入時には売買契約書に貼り付けて使用します。 印紙税は収入印紙購入時に支払うことになります。不動産売買契約書の印紙税の税額は以下のとおりです。
| 契約金額 | 税金(軽減税率) |
|---|---|
| 0円〜1万円未満 | 非課税 |
| 10万円〜50万円以下 | 400円(200円) |
| 50万円〜100万円以下 | 1千円(500円) |
| 100万円〜500万円以下 | 2千円(1千円) |
| 500万円〜1,000万円以下 | 1万円(5千円) |
| 1,000万円〜5,000万円以下 | 2万円(1万円) |
| 5,000万円〜1億円以下 | 6万円(3万円) |
| 1億円〜5億円以下 | 10万円(6万円) |
| 5億円〜10億円以下 | 20万円(16万円) |
参考:国税庁(不動産売買契約書の印紙税の軽減措置)
参考:国税庁(印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで)
契約金額が高くなると税金も高くなります。
なお、売買契約書に印紙を添付しなければ「過怠税」として契約金額の3倍の支払いを求められる可能性があるので注意しましょう。
■ 手数料とともに支払う「消費税」
不動産会社の仲介手数料や司法書士の手数料などに対し、報酬とは別途10%の消費税が発生します。なお、個人の自宅および土地の売却本体に消費税は発生しません。
■ 住宅ローンの抵当権抹消の際の「登録免許税」
抵当権とは、住宅購入時に金融機関が住宅ローンを完済するまで設定する権利のことです。そのため、家を売却するためには住宅ローンを完済し、抵当権を抹消する必要があります。土地と建物にそれぞれ1,000円の登録免許税がかかります。■ 自宅の売却益に対する「譲渡税」
自宅を売却し儲かった場合、譲渡税が発生します。ただし、自宅の売却には特例制度が設けられておりますので、こちらの制度を利用することができれば税金を納めなくてよいこともあります。
詳しい譲渡税の計算方法は、次項で紹介します。
なお、譲渡税というのはよく使われる用語ですが、実際には「譲渡税」という税金はなく、売却益に対して課税される所得税及び住民税のことを略して譲渡税と呼びます。
譲渡税の計算方法
計算の流れ
税金を正しく計算するために3つの段階に分けて解説します。【STEP1】 譲渡所得の計算
譲渡所得=売却代金-(取得費+譲渡費用)
【STEP2】 特別控除
課税所得=譲渡所得-特別控除
【STEP3】 譲渡税
譲渡税=課税所得×税率
【STEP1】 譲渡所得の計算(譲渡所得=売却代金-(取得費+譲渡費用))
(1)取得費とは「自宅購入時に要した費用から経年劣化の価値を減少させたもの」です。
以下のものがあります。
● 自宅購入代金・建築代金
● 不動産取得税
● 登記費用(司法書士報酬を含みます)
● 印紙税
● 仲介手数料
● 測量費や土地の造成費用等
上記の合計額から経年劣化に相当する「自宅建物の償却費の累積額」を控除します。
(2)譲渡費用とは
譲渡費用とは「売却の際にかかった費用」のことです。
費用に含まれる主な項目は以下のとおりです。
● 印紙税
● 仲介手数料
● 建物の取り壊し費用等
【STEP2】 特別控除(課税所得=譲渡所得―特別控除)
一般の不動産売却には「特別控除」はありません。自宅売却で「居住用財産」の要件を満たす場合、譲渡所得から特別控除3,000万円を控除できます。
「居住用財産」の要件に関しては、次項で解説します。
【STEP3】 譲渡税(譲渡税=課税所得×税率)
(1)通常の税率不動産売却における税率は、所有期間で以下のように異なります。
| 所有期間 | 税率 |
|---|---|
| 短期譲渡所得 (所有期間5年以下) |
39.63% (所得税30%、住民税9%、復興所得税0.63%) |
| 長期譲渡所得 (所有期間5年超) |
20.315% (所得税15%、住民税5%、復興所得税0.315%) |
(2)特例の税率
マイホームの売却が要件を満たすと、軽減税率が適用できます。要件については次項で解説します。
譲渡税がゼロに!?自宅を売却した際の特例制度を解説!
自宅の売却が要件を満たすと様々な特例制度が活用できます。特例制度が利用できれば大半の人は譲渡税がかからなくなります。特例制度が利用できる要件を事前に確認し、無駄な税金を払わなくてよいようにしましょう。
(1)売却益が発生した場合の特例制度一覧
① 3,000万円の買い替え特例
③ 軽減税率
(2)売却損が発生した場合の特例制度一覧
① マイホームを買い替えた場合の損益通算と繰越控除
② 特定マイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
(3)3,000万円の特別控除
売却益(譲渡所得)から3,000万円の控除が受けられる制度です。
売却益が3,000万円以下の場合は税金の支払いは必要ありません。
① 要件
イ 「居住用財産の売却」であること
以下の要件を満たす売却をいいます
・自分が住んでいる家屋の売却
・自分が住んでいる家屋とともにその敷地の売却
・住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却
ロ 所有期間
問いません
ハ 親族以外への譲渡でないこと等
② 併用可能な特例制度
・軽減税率との併用が可能です。
③ 併用不可な特例制度
・次のマイホームに一定期間ローン控除が使えなくなります。
・マイホームの買い替え特例
(4)マイホームの買い替え特例
マイホームを買い替えた場合で下記の要件を満たす場合、買い替え特例が使えます。ただし、この特例は課税の繰り延べのため税金の軽減ではありません。3,000万円控除を優先的に利用することを考えましょう。
① 要件
イ 「居住用財産の売却」であること
以下の要件を満たす売却をいいます
・自分が住んでいる家屋の売却
・自分が住んでいる家屋とともにその敷地の売却
・住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却
ロ 所有期間・居住期間
10年以上居住し、かつ、10年超所有する必要があります。
ハ その他売却代金が1億円以下であること等
② 併用不可な特例制度
・特別控除3,000万円との併用ができません。
・次のマイホームに一定期間ローン控除が使えなくなります。
・軽減税率との併用ができません。
(5)軽減税率の特例
10年を超えて所有している「居住用不動産」の売却益に対する譲渡税の税率が低くなる特例です。
① 要件
イ 「居住用財産の売却」であること
以下の要件を満たす売却をいいます
・自分が住んでいる家屋の売却
・自分が住んでいる家屋とともにその敷地の売却
・住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却
ロ 所有期間・居住期間
10年超所有する必要があります。
② 併用可能な特例制度
・特別控除3,000万円との併用が可能です。
➂ 併用不可な特例制度
・次のマイホームに一定期間ローン控除が使えなくなります。
・マイホームの買い替え特例
④ 税率
| 譲渡所得 | 税率 |
|---|---|
| 6,000万円以下の部分 | ・所得税:10.21% ・住民税:4% ・合計:14.21% |
| 6,000万円以上の部分 | ・所得税:15.315% ・住民税:5% ・合計:20.315% |
売却損をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。 さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった売却損は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。
① 要件
イ 「居住用財産の売却」であること
以下の要件を満たす売却をいいます
・自分が住んでいる家屋の売却
・自分が住んでいる家屋とともにその敷地の売却
・住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却
ロ 所有期間
5年超であることが必要です。
ハ 買い替えたマイホームに10年以上の住宅ローンがあること等
② 併用可能な特例制度
・住宅ローン控除との併用が可能です。
(7)特定マイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
一定の売却損をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。
さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった売却損は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。
① 要件
イ 「居住用財産の売却」であること
以下の要件を満たす売却をいいます
・自分が住んでいる家屋の売却
・自分が住んでいる家屋とともにその敷地の売却
・住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却
ロ 所有期間
5年超であることが必要です。
ハ 売却したマイホームに売却代金で返済しきれない住宅ローンが残っていること等
① 併用可能な特例制度
・次の購入したマイホームの住宅ローン控除との併用が可能です。
確定申告は必要?譲渡税ゼロでも確定申告が必要な場合も
(1)確定申告が必要なケース
以下の3つです。
● 譲渡益が発生した場合
● 3,000万円の特別控除を適用し、譲渡益がゼロになった場合
● 譲渡損失が発生し、損益通算・損失の繰越控除を適用する場合
特例を利用する場合は、税金が発生しなくても確定申告が必要です。注意しましょう。
(2)確定申告のタイミング
「不動産を売却した日の翌年2月16日から3月15日頃」です。 タイミングによっては1年以上先になる場合もありますが、特例を利用する場合は忘れず申告しましょう。
税金を正しく理解して、次のマイホーム購入計画を
不動産の売却後に多額の税金が発生して、思ったよりお金が残らなかったという話をよく耳にします。
次のマイホーム購入の際の資金計画にずれが出ないようにするには正しい税額を把握しておく必要があります。
この記事で紹介したこと以外にも、さまざまな注意点があるので、税金に関する不安がある方は信頼できる税理士に相談してみましょう。
また、家を売却して新築で注文住宅を検討している方は、ランディでの土地探しがおすすめです。
ランディPRO導入店のハウスメーカーや工務店に来場することで、複雑な計算ができる住替えに対応した資金計画システムや、マンションの売却価格の査定システムなどを使って住替えサポートもしてくれます。
お困りのことがある方は、悩む前にランディPRO導入店に相談してみましょう。
家を売却して新築で注文住宅を検討している方は、非公開物件情報も含めた全売土地情報からまとめて探せる「ランディ アプリ」で土地探しをしてみてください。